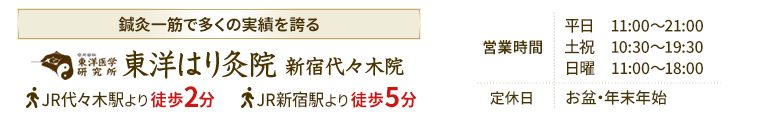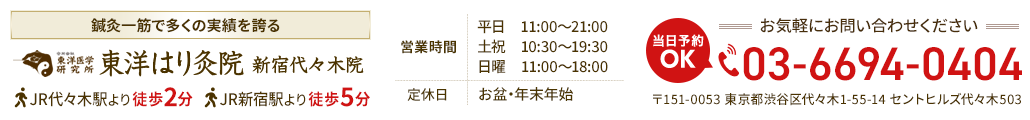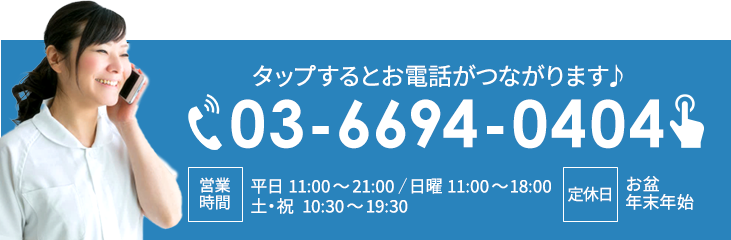「30代からの不調」原因は機能の低下だった?

東洋はり灸院 院長の石丸です。
今回はYouTubeの視聴者の方からご質問をいただきましたので、その質問に対する回答をしていきたいと思います。
質問内容

30代中盤になってから寝違えやすく、背中、首、肩のこりを感じやすくなりました。ここ数年、不調になる度、根本治療を求めて接骨院や整体、鍼灸院に行くのですが、「胸椎の5番がやや奥にあるのが原因かもしれない」と言われます。他の動画を拝見したところ、東洋医学では火事の火の元(原因)によって煙(不調)が表に出ているとのことですが、この業界でよく治療師が口にする体の骨、姿勢の歪みも表に出ている不調の1つなのでしょうか?
動画解説「30代からの不調の原因」
不調が起こる2つの原因

30代中盤になってから不調が出てきて、胸椎の5番が奥にずれていることが原因だと言われたとのことですが、私は柔道整復師の免許を持ち、整骨院を運営する資格があります。また、整形外科やカイロプラクティック、鍼灸整骨院でも働いた経験があります。そのような経験を通じて、いつもお話しさせていただいていることがあります。
人間の体を蛍光灯に例えたときに、蛍光灯が点灯しない場合には、主に2つの原因が考えられます。
1つは、蛍光灯自体が壊れてしまった場合や、点灯に必要な配線が切れてしまっているなど、構造的な異常によるものです。構造物に問題がある場合は、電気が供給されても蛍光灯は点きません。
もう1つは、ブレイカーが落ちている場合や、電気会社から電気が止められている場合など、電気の供給自体が止まっている状態です。この場合も、電気が届かないため、当然蛍光灯は点灯しません。
蛍光灯が点灯しない原因はこの2つに大別されますが、質問者様がおっしゃった「頸椎の5番が奥にある」というのは、蛍光灯の例えで言えば「蛍光灯自体に異常があるために電気が点かない」という状況と同じです。

これは何度もお話ししていることですが、病院を含めた多くの治療院は西洋医学を基盤としています。私が過去に働いてきた整形外科や整骨院なども基本的に西洋医学です。西洋医学は構造的な異常を観察し、その原因を追究する医学なので、不調の原因は構造的な異常にあると考える傾向にあります。
そのため、東洋医学を実践していなければ、「電気がきていないから蛍光灯が点かない」という着眼点にはならないのです。
加齢による機能の低下

今回のご質問では、「30代中盤になってから不調を感じるようになった」とのことです。質問者様も薄々は気づいていらっしゃるかもしれませんが、30代中盤になるということは、10代や20代のころの体ではなくなってきたということです。
この点を踏まえると、実際にお会いして施術を行わなければ正確にはわかりませんが、「電気がきていない」つまり体力や免疫力、体の機能が低下してきたことによって症状が出ている可能性が高いのではないかと考えます。
また、胸椎の5番が奥に行っていることが原因だとした場合、では、どう対処するのかという話にもなります。これが本当に1つの要因である可能性はあります。先ほど、蛍光灯を例に構造物の異常と機能の低下についてご説明しましたが、実はこの両方が組み合わさっているケースもあります。
蛍光灯が割れてしまっていれば、当然、蛍光灯は点灯しません。ヘルニアが飛び出していて神経にあたっている場合や、骨折、靭帯断裂などのケースがこれに該当します。このように、明らかに構造物に異常がある場合は、痛みや強い症状が出るはずです。
しかし、年齢を重ねるごとに誰でも変化をしていきます。私も10代と比べると、体の構造もすっかり変わっています。この衰退が、症状に直結する領域に達することもありますが、一方で、年齢を重ねるとともに機能も低下するため、電気を送る力も落ちていきます。つまり、加齢に伴い、構造物の劣化と機能の低下の両方が同時に起こるのです。
したがって、質問者様の不調の原因がどちらか一方だけにあるとは断定できませんが、30代中盤という年齢を考えると、機能の低下によるものである可能性が高いと私は考えます。
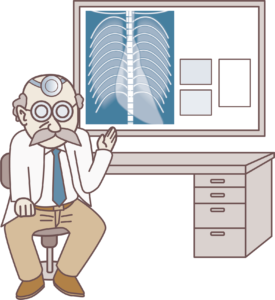
当店のお客様の中には100歳の方もいらっしゃいますが、この方と35歳中盤の質問者様の年齢差は約65歳です。レントゲン検査をすると、おそらく100歳のお客様の骨の方が構造上は乱れていると思いますが、その方は首や肩の痛みを一切訴えていません。このことからも、質問者様の不調は構造的な原因ではなく、機能的、つまり東洋医学的な要素に原因がある可能性が高いと考えられます。
もちろん、質問者様が道を歩いている時に自転車や車に衝突されたなど、その瞬間に構造物が壊れた場合は別ですが、普通の生活の中で徐々に症状が出ているのであれば、胸椎の5番にこだわりすぎる必要はないと思います。
東洋医学の観点を取り入れる
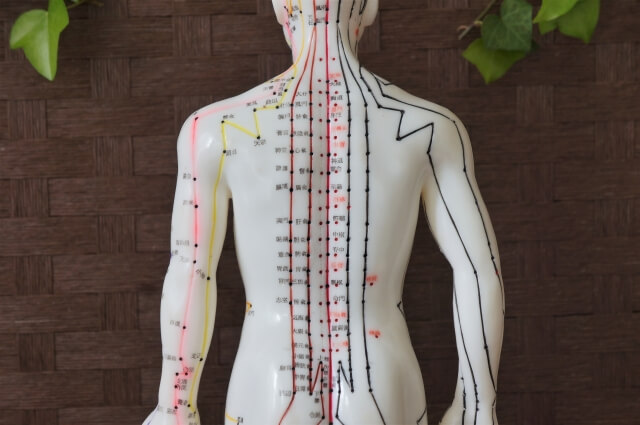
私は20年以上前に2~3年ほどカイロプラクティックに携わっていましたが、その経験から、多くの人は背骨が曲がっていたり、左右の足の長さに違いがあったりすることが多いと感じています。足を組むときに、右足の方が組みやすい、左足の方が組みやすいということはないでしょうか。また、うつ伏せで寝たときに、頭を右に向けると引っかかるなど、楽な方向や癖があると思います。
このような構造的なゆがみや欠陥は、多くの場合、症状には直結しない範囲内であることがほとんどです。
しかし、多くの病院や治療院は西洋医学の考え方が主流であるため、不調は構造的な欠陥によるものだと捉えがちです。今回の質問者様の通っている接骨院や整体の多くも、西洋医学を軸として目に見える物だけを扱っています。ここで構造物の欠陥を指摘され、施術によって改善するのであれば問題ありません。
しかし、改善されない場合は、観点を変え、東洋医学という世界観も取り入れる必要があると思います。
質問者様は鍼灸院にも行かれたそうですが、実際には鍼灸院でさえその多くが西洋医学を基盤としています。なぜなら、鍼灸師の学校で学ぶ内容の大部分が西洋医学に関するものだからです。そのため、東洋医学を専門に扱う鍼灸院に行かなければ、改善は難しいと考えられます。
おわりに

今回のご質問への回答はこのようになります。ご質問いただき、ありがとうございました。
最後まで読んで頂いた皆さまの参考になれば、嬉しく思います。